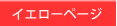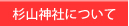| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央1-14-1 |
| 御由緒 | 鶴見神社は往古は杉山大明神と称し、境内地約五千坪を有する社でありました。その創建は推古天皇の御代(約1400年前)と伝えられております。続日本後記承和五年(約1180年前)2月の頃に「武蔵国都筑郡杉山の社、霊験あるを以って官幣を之に預らしむ。」とあります。この有力神社として江戸時代の国学者黒川春村は「杉山明神神寿歌釈」(鶴見神社に伝わる田祭りに関する本)の中に書き残しております。大正9年に鶴見神社と改称されました。昭和37年、境内より弥生式後期から土師「古墳時代」を中心として鎌倉期に及ぶ、多数の祭りに使用された道具が発見され、推古天皇以前より神聖な地として、すでに祭が行われていたことと共に、横浜・川崎間最古の社である事が立証されました。横浜最古の神事芸能田遊びは、明治4年を最後に廃絶となりましたが、昭和62年に再興されました。以来杉山祭と呼称して田祭り保存会が結成され、毎年例祭日に奉納されております。のちに天王宮が合祀されて二社相殿となりまた天王宮の大神輿は、鶴見川に流れついたと言い伝えられる横浜最古の神輿で、毎年古式豊かに渡御され、天王祭として盛大に取り行なわれております。 |
| 御祭神 | 杉山大明神 五十猛命 天王宮 素盞鳴尊 |






杉山神社リストへ戻る