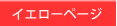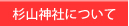あかね台1丁目に「上恩田杉山神社」があります。そして、地図を見てもらえば判るとおり、杉山神社という名前の社は、このあかね台だけでなく、すぐ隣の成瀬をはじめ、青葉区、緑区、都筑区、港北区など横浜市北部を中心に数多くあることに気付きました。
当然、「杉山神社ってなんだろう?」という疑問を持ちました。もちろん、ネットで調べれば疑問に対するそれなりの答えは見つかります。と同時に、杉山神社には、「数多い社のうちの本祠は何処なのか?」とか「本来の御祭神(=お祭りしている神様)はどれなのか?」といった、郷土史家の間でも解決されていない疑問があることが判りました。
以下は、今までに発表されている様々な説を、まとめてみたものです。杉山神社入門といったところでしょうか。
杉山神社とは
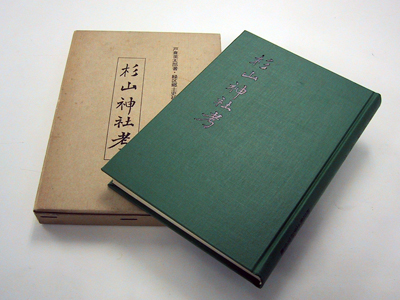 杉山神社は、都筑郡で唯一の式内社である、というのが、史家にとっては大きく興味を惹かれるところです。
杉山神社は、都筑郡で唯一の式内社である、というのが、史家にとっては大きく興味を惹かれるところです。
式内社といわれてもピンときませんよね。この式内社とは延喜式の神名帳に記されている神社のことを言います。延喜式とは、その名のとおり延喜5年(905年)に朝廷の詔命のもと編纂がスタートした法典のことです。実際にこの延喜式が施行されたのは康保4年(967年)ということですから、実に62年間にわたって編纂・修訂がされたことになります。また、その数、全50巻になります。
その延喜式の中に神名帳という神社のリストがあるのです。記載された神社の数は、全国で2,861社になります。つまり、ここに記載された神社は、いわば、その時代に国からオーソライズされていた神社ということで、今で言えば由緒正しき社ということになるのです。
当時は京が都でしたので、式内社は京都内やその周辺が当然ながら多くなります。都から遠く離れた都筑郡では唯一、杉山神社が式内社とされたのです。
参考までに、都筑郡とは、7世紀の律令制度で決められてた武蔵国都筑郡のことで、現代では、横浜市都筑区、青葉区、緑区と、港北区、保土ケ谷区、旭区、川崎市麻生区の一部を加えたエリアです。因みに、武蔵国は22郡あり、都筑郡の他は、豊島郡、葛飾郡、荏原郡、橘樹郡、久良岐郡、多摩郡、新座郡、足立郡、入間郡、高麗郡、比企郡、横見郡、埼玉郡、大里郡、男衾郡、幡羅郡、榛沢郡、那賀郡、児玉郡、賀美郡、秩父郡となります。都筑郡の近隣は、橘樹郡(横浜市・鶴見区、神奈川区、保土ケ谷区、港北区一帯)、久良岐郡(南区、中区、磯子区、金沢区と、港南区、西区の一部)になります。
杉山神社と忌部氏
式内社としてオーソライズされたにもかかわらず、不思議なことに杉山神社のルーツについては、確固とした定説がありません。というのも由緒らしい由緒が何処にも残っていないからです。参考になる資料のひとつとしては、センター南駅前の都筑中央公園の中にある杉山神社には「勅願所式内武蔵國都筑郡之一座當國三ノ宮枌山神社祭神由布津命 傅記云由布津命ハ天日鷲命之孫也 天武天皇白鳳三年九月堅田主命二十代ノ孫忌部勝麻呂依御霊而奏天朝武蔵國枌山乃國ニ立神籬右大神ヲ奉リ枌山社ト號シ奉ル」とあります。つまり、白鳳3年(674年)に忌部勝麻呂が、由布津主命を奉って枌山神社としたというのです。斉主は、その勝麻呂の弟である義麻呂が就き、以降、歴代の斉主は、忌部義麻呂という名を引き継いでいます。なお、枌山は「すぎやま」と読みます。椙山も同様に「すぎやま」と読みます。
ここに出てくる忌部氏は、太玉命を遠祖に持ち、大和時代から神事に関わってきた有力氏族です。祭官として力を持つ忌部氏は、その一族も全国に広がっています。忌部氏のうちの一派である阿波忌部氏は東国に進出した氏族です。千葉県館山市にある安房神社は阿波忌部氏が建立した神社ですが、安房神社の安房は阿波忌部氏の出身である阿波(=香川)の名なのです。
その東国に勢力を持っていた忌部氏のひとりである忌部勝麻呂が杉山神社を建立したというのが、杉山神社の由緒のひとつの説となっています。なお、忌部氏は、その後、朝廷で同じく神事に関わってきた中臣氏(=藤原氏)との勢力争いに負け、中央の政治の舞台から遠のいていってしまいます。そのため、杉山神社が式内社でありながら、その由緒も祭神も判らなくなってしまったのには、忌部氏の衰退と関わりがあるのではという意見もあるようです。
杉山神社はいくつある
では、杉山神社は何故こんなにあるのでしょうか。
その答えは簡単です。式内社としての杉山神社ですから、格式もあり霊験あらたかでありということで、おらが村にもそんなえらい神様をお迎えしたいということで、分祀されたり肖ったりで(このことを勧請するなどと言います)どんどんと数が増えていったのでしょう。全国規模では、氷川神社とか住吉神社が数多くあるのと同じです。
記録に残っているものでは、江戸時代に編纂された「新編武蔵風土記稿(1810〜1830年・全266巻)」によれば、都筑郡に24社、橘樹郡に37社、久良岐郡に5社、南多摩郡に6社と、計72社が分布したとあります。現在で言えば、横浜市内50社、川崎市内16社、東京都(町田市・稲城市)に6社となります。その分布は、主に鶴見川とその支流(早淵川、矢上川、大熊川、恩田川、奈良川など)に集中していて、多摩川を渡った所には1社もないという特徴があります。
しかし、その後、廃社されたり、他の神社と合祀(いわゆる神社の合併)されたりとしてしまったため、現存ではそのすべてを確認することはできません。また、ほとんど由緒書などが残っておらず、文書からその歴史を調べることができないというのが現実です。
杉山神社の本祠はどこだ
では、延喜式に記された杉山神社は、現在のどの杉山神社なのでしょうか。これも史家の間で論争されるところです。そして、先述したとおり、由緒書などが残っていない実情では、これといった決定的な証拠がないままです。例え、由緒書などがあっても、それは、ここの杉山神社はこうだと伝わっているということを、近年になって記しているだけで、説得力に乏しいものばかりなのです。
更に言えば明治39年(1906年)に政府から神社合祀令という無茶な政策が発令されたお陰で、日本の神社の由緒が判らなくなるようなことに拍車がかかりました。この神社合祀令は、具体的には一村一社にしなさいという命令です。つまり、ひとつの村に複数神社がある場合は、それら神社を合併してひとつの神社にしなさいというものなのです。これによってA神社とB神社を合併してC神社にするとか、B神社とC神社はA神社に吸収合併するとかいうことが起こりました。何だか企業のM&Aのようです。そのため、杉山神社も今では他の神社に合祀されてしまっているケースもあり、よけいに本来の由緒があやふやになってしまっています。
現在、杉山神社の本祠として候補にあがっている(?)のが、新吉田、茅ヶ崎中央、中川、勝田、西八朔、星川、鶴見(鶴見神社)です。ちなみに、歴史用語では本祠の候補になっている社のことを「論社」といいます。なお、旧地名で大棚にあったとされる中川の杉山神社は、土地区画整理で昭和58年(1983年)に移転してしまっていますので、例え本祠であっても現存していないことになります。
御祭神は誰なのか
通常、御祭神については、祖を同じくする神社であれば、多少のブレはあるものの、同じ神様をお祭りしているというのが普通です。
ところが杉山神社の御祭神は、統一がありません。大雑把に言うと、五十猛命(いそたけるのみこと・いたけるのみこと)と日本武尊(やまとたけるのみこと)が半々に奉られています。また、大己貴命(おおなむちのみこと)や素盞嗚命(すさのおのみこと)が合祀されている場合も見られます。
日本書紀によれば五十猛命は素盞嗚命の子です。大己貴命は、日本書紀によれば素盞嗚命の子、古事記では、素盞嗚命の六世の孫とされています。大己貴命は、大国主神、大物主神、大國魂大神と同一神です。
一方、日本武尊は第十二代景行天皇の子とされています。というよりも、神話の中でもポピュラーな英雄なので、広く知られている存在でしょう。
神話に詳しい方ならお判りでしょうが、日本は大和朝廷民族が、それ以前に勢力を誇っていた民族を倒して成立したということになっています。まつろわぬ神々と呼ばれる非征服民族が国つ神、そして、征服民族が天つ神として後に神格化されるわけです。
この分類で言うと、素盞嗚命・五十猛命・大己貴命は国つ神であり、天照大神・日本武尊は天つ神となります。同じ神社でありながら、これが真っ二つに別れるというのは不思議なことです。尤も、天つ神と国つ神を御祭神とすることは珍しくありません。主に、被征服者の国つ神を祭って、その国つ神を鎮めるために(祟らないようにするために)天つ神を一緒にするというのが、主な理由です(祟りということに関しては井沢元彦氏あたりの書を読んでみてください)。
しかし、五十猛命だけを奉っていたり、日本武尊だけを奉っていたりというのが、これほどまでに二分されているのは非常にレアなケースともいえるでしょう。
とは言え、御祭神にしても本祠にしても、定説がない、判らないというのは、史家の心をくすぐるようで、今なお、主に郷土史家の間で研究が進められています。
杉山神社リストへ
当然、「杉山神社ってなんだろう?」という疑問を持ちました。もちろん、ネットで調べれば疑問に対するそれなりの答えは見つかります。と同時に、杉山神社には、「数多い社のうちの本祠は何処なのか?」とか「本来の御祭神(=お祭りしている神様)はどれなのか?」といった、郷土史家の間でも解決されていない疑問があることが判りました。
以下は、今までに発表されている様々な説を、まとめてみたものです。杉山神社入門といったところでしょうか。
杉山神社とは
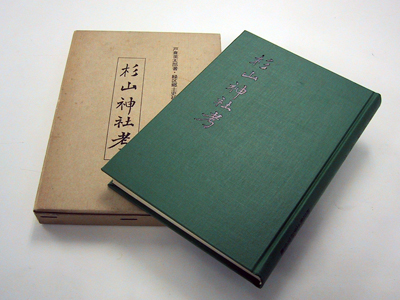 杉山神社は、都筑郡で唯一の式内社である、というのが、史家にとっては大きく興味を惹かれるところです。
杉山神社は、都筑郡で唯一の式内社である、というのが、史家にとっては大きく興味を惹かれるところです。式内社といわれてもピンときませんよね。この式内社とは延喜式の神名帳に記されている神社のことを言います。延喜式とは、その名のとおり延喜5年(905年)に朝廷の詔命のもと編纂がスタートした法典のことです。実際にこの延喜式が施行されたのは康保4年(967年)ということですから、実に62年間にわたって編纂・修訂がされたことになります。また、その数、全50巻になります。
その延喜式の中に神名帳という神社のリストがあるのです。記載された神社の数は、全国で2,861社になります。つまり、ここに記載された神社は、いわば、その時代に国からオーソライズされていた神社ということで、今で言えば由緒正しき社ということになるのです。
当時は京が都でしたので、式内社は京都内やその周辺が当然ながら多くなります。都から遠く離れた都筑郡では唯一、杉山神社が式内社とされたのです。
参考までに、都筑郡とは、7世紀の律令制度で決められてた武蔵国都筑郡のことで、現代では、横浜市都筑区、青葉区、緑区と、港北区、保土ケ谷区、旭区、川崎市麻生区の一部を加えたエリアです。因みに、武蔵国は22郡あり、都筑郡の他は、豊島郡、葛飾郡、荏原郡、橘樹郡、久良岐郡、多摩郡、新座郡、足立郡、入間郡、高麗郡、比企郡、横見郡、埼玉郡、大里郡、男衾郡、幡羅郡、榛沢郡、那賀郡、児玉郡、賀美郡、秩父郡となります。都筑郡の近隣は、橘樹郡(横浜市・鶴見区、神奈川区、保土ケ谷区、港北区一帯)、久良岐郡(南区、中区、磯子区、金沢区と、港南区、西区の一部)になります。
杉山神社と忌部氏
式内社としてオーソライズされたにもかかわらず、不思議なことに杉山神社のルーツについては、確固とした定説がありません。というのも由緒らしい由緒が何処にも残っていないからです。参考になる資料のひとつとしては、センター南駅前の都筑中央公園の中にある杉山神社には「勅願所式内武蔵國都筑郡之一座當國三ノ宮枌山神社祭神由布津命 傅記云由布津命ハ天日鷲命之孫也 天武天皇白鳳三年九月堅田主命二十代ノ孫忌部勝麻呂依御霊而奏天朝武蔵國枌山乃國ニ立神籬右大神ヲ奉リ枌山社ト號シ奉ル」とあります。つまり、白鳳3年(674年)に忌部勝麻呂が、由布津主命を奉って枌山神社としたというのです。斉主は、その勝麻呂の弟である義麻呂が就き、以降、歴代の斉主は、忌部義麻呂という名を引き継いでいます。なお、枌山は「すぎやま」と読みます。椙山も同様に「すぎやま」と読みます。
ここに出てくる忌部氏は、太玉命を遠祖に持ち、大和時代から神事に関わってきた有力氏族です。祭官として力を持つ忌部氏は、その一族も全国に広がっています。忌部氏のうちの一派である阿波忌部氏は東国に進出した氏族です。千葉県館山市にある安房神社は阿波忌部氏が建立した神社ですが、安房神社の安房は阿波忌部氏の出身である阿波(=香川)の名なのです。
その東国に勢力を持っていた忌部氏のひとりである忌部勝麻呂が杉山神社を建立したというのが、杉山神社の由緒のひとつの説となっています。なお、忌部氏は、その後、朝廷で同じく神事に関わってきた中臣氏(=藤原氏)との勢力争いに負け、中央の政治の舞台から遠のいていってしまいます。そのため、杉山神社が式内社でありながら、その由緒も祭神も判らなくなってしまったのには、忌部氏の衰退と関わりがあるのではという意見もあるようです。
杉山神社はいくつある
では、杉山神社は何故こんなにあるのでしょうか。
その答えは簡単です。式内社としての杉山神社ですから、格式もあり霊験あらたかでありということで、おらが村にもそんなえらい神様をお迎えしたいということで、分祀されたり肖ったりで(このことを勧請するなどと言います)どんどんと数が増えていったのでしょう。全国規模では、氷川神社とか住吉神社が数多くあるのと同じです。
記録に残っているものでは、江戸時代に編纂された「新編武蔵風土記稿(1810〜1830年・全266巻)」によれば、都筑郡に24社、橘樹郡に37社、久良岐郡に5社、南多摩郡に6社と、計72社が分布したとあります。現在で言えば、横浜市内50社、川崎市内16社、東京都(町田市・稲城市)に6社となります。その分布は、主に鶴見川とその支流(早淵川、矢上川、大熊川、恩田川、奈良川など)に集中していて、多摩川を渡った所には1社もないという特徴があります。
しかし、その後、廃社されたり、他の神社と合祀(いわゆる神社の合併)されたりとしてしまったため、現存ではそのすべてを確認することはできません。また、ほとんど由緒書などが残っておらず、文書からその歴史を調べることができないというのが現実です。
杉山神社の本祠はどこだ
では、延喜式に記された杉山神社は、現在のどの杉山神社なのでしょうか。これも史家の間で論争されるところです。そして、先述したとおり、由緒書などが残っていない実情では、これといった決定的な証拠がないままです。例え、由緒書などがあっても、それは、ここの杉山神社はこうだと伝わっているということを、近年になって記しているだけで、説得力に乏しいものばかりなのです。
更に言えば明治39年(1906年)に政府から神社合祀令という無茶な政策が発令されたお陰で、日本の神社の由緒が判らなくなるようなことに拍車がかかりました。この神社合祀令は、具体的には一村一社にしなさいという命令です。つまり、ひとつの村に複数神社がある場合は、それら神社を合併してひとつの神社にしなさいというものなのです。これによってA神社とB神社を合併してC神社にするとか、B神社とC神社はA神社に吸収合併するとかいうことが起こりました。何だか企業のM&Aのようです。そのため、杉山神社も今では他の神社に合祀されてしまっているケースもあり、よけいに本来の由緒があやふやになってしまっています。
現在、杉山神社の本祠として候補にあがっている(?)のが、新吉田、茅ヶ崎中央、中川、勝田、西八朔、星川、鶴見(鶴見神社)です。ちなみに、歴史用語では本祠の候補になっている社のことを「論社」といいます。なお、旧地名で大棚にあったとされる中川の杉山神社は、土地区画整理で昭和58年(1983年)に移転してしまっていますので、例え本祠であっても現存していないことになります。
御祭神は誰なのか
通常、御祭神については、祖を同じくする神社であれば、多少のブレはあるものの、同じ神様をお祭りしているというのが普通です。
ところが杉山神社の御祭神は、統一がありません。大雑把に言うと、五十猛命(いそたけるのみこと・いたけるのみこと)と日本武尊(やまとたけるのみこと)が半々に奉られています。また、大己貴命(おおなむちのみこと)や素盞嗚命(すさのおのみこと)が合祀されている場合も見られます。
日本書紀によれば五十猛命は素盞嗚命の子です。大己貴命は、日本書紀によれば素盞嗚命の子、古事記では、素盞嗚命の六世の孫とされています。大己貴命は、大国主神、大物主神、大國魂大神と同一神です。
一方、日本武尊は第十二代景行天皇の子とされています。というよりも、神話の中でもポピュラーな英雄なので、広く知られている存在でしょう。
神話に詳しい方ならお判りでしょうが、日本は大和朝廷民族が、それ以前に勢力を誇っていた民族を倒して成立したということになっています。まつろわぬ神々と呼ばれる非征服民族が国つ神、そして、征服民族が天つ神として後に神格化されるわけです。
この分類で言うと、素盞嗚命・五十猛命・大己貴命は国つ神であり、天照大神・日本武尊は天つ神となります。同じ神社でありながら、これが真っ二つに別れるというのは不思議なことです。尤も、天つ神と国つ神を御祭神とすることは珍しくありません。主に、被征服者の国つ神を祭って、その国つ神を鎮めるために(祟らないようにするために)天つ神を一緒にするというのが、主な理由です(祟りということに関しては井沢元彦氏あたりの書を読んでみてください)。
しかし、五十猛命だけを奉っていたり、日本武尊だけを奉っていたりというのが、これほどまでに二分されているのは非常にレアなケースともいえるでしょう。
とは言え、御祭神にしても本祠にしても、定説がない、判らないというのは、史家の心をくすぐるようで、今なお、主に郷土史家の間で研究が進められています。
杉山神社リストへ