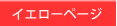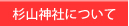| 皇国地誌は明治政府によって企画・編纂された官撰地誌です。明治12年に神奈川県令に提出された恩田村の村誌を下記に転載します。 | |
| 【村誌】 | |
| 武蔵国都筑郡恩田村 支村新田なし 本村往古の名称詳かならず 本郡に属し小机領恩田村と称す 後年歴詳かならず冠称を廃す | |
| 【疆域(きょうり)】 | |
| 東本郡下谷本村に界し 西本国多摩郡成瀬村に通じ 南本郡長津田村に接し 北本郡鴨志田村及び成合村に接し 東南本郡十日市場村に界し 東南東本郡西八朔村に接し 東北本郡上谷本村に連り 西北本郡奈良村に隣す | |
| 【幅員】 | |
| 東西千八百八十八間南北千弐百四十弐間 | |
| 【沿革】 | |
| 往古の事跡詳かならず 大永の頃より天正年間迄小田原北條氏の属臣小机城主笠原越前守信為子孫三世本村を領す 天正十八年庚寅北條氏滅して徳川氏これに代り代官支配所となり 文禄年間大久保石見守の領地となり 元和年間堀田出羽守領地に代り 寛永年間又徳川氏の直轄となり 代官成瀬五左衛門これを支配す 元禄年間本村高千百三拾七石五斗九升三合四勺四才を分割して五百五拾石三升医師岡本玄治の釆地に給し 弐百七拾八石九斗四升三合三勺八才旗本柳沢八郎右衛門に給し 百八拾五石九斗五升三合三勺同朝岡彦次郎に給し 六拾三石三斗八升四合同星合伊左衛門に給し 五拾四石四斗九升七合五勺医師船橋長庵に給し 四拾八石二斗三升三合旗本井戸甚助に給す 六氏これを世襲し 明治元戊辰年八月品川県の所管となり 同年九月更に神奈川県所轄に帰す | |
| 【里程】 | |
| 神奈川県庁を距たる西北の方五里拾九町三拾五間三尺 | |
| 【近傍宿町】 | |
| 東南の方神奈川駅元標に至る四里拾七町拾七間三尺 南の方保土ケ谷駅元標に至る四里壱町五拾壱間三尺 | |
| 【四隣村々】 | |
| 東の方本郡下谷本村元標に至る壱里七町拾九間 西の方本国多摩郡成瀬村元禄に至る弐拾三町拾八間 南の方本郡長津田村元標に至る拾四町五拾間 北の方本郡鴨志田村元標に至る弐拾壱町三拾九関 同 本郡成合村元標に至る弐拾八町四拾間 東南の方本郡十日市場村元標に至る三拾三町八間 東南東の方本郡西八朔村元標に至る三拾壱町弐拾九関 東北の方本郡上谷本村元標に至る弐拾九町四拾四間 西北の方本郡奈良村元標に至る拾三町五拾七間三尺 但し元標本村三千三百六拾三番地西南々の方村往還の側字山ケ谷(やまがやと)通にあり | |
| 【地勢】 | |
| 全村岡阜(こうふ)起伏し 丘間に田土開け、南境に恩田川の小流を帯び 南の一面平坦にして田圃開け 運輸不便薪炭乏しからず | |
| 【地味】 | |
| 黒壚土(くろまつち)居多く 赤土を雑土(まぜつち)でその色黒その質中等 菽(まめ) 麦 粟 稗に適し、桑に可なり その他の諸植物に宜しからず 水利不便にして時々旱(ひでり)に苦しむ 税地総反別五百五拾弐町八反十六歩 地価八万弐千六百八拾八円九拾壱銭 田八拾六町五反五畝拾四歩 地価四万八千九百拾円七拾七銭 畑百六拾六町七反五畝二十四歩 同弐万五千九百七拾弐円九拾四銭 宅地拾七町六反四畝拾七歩 同四千五百六拾三円五銭弐厘 山林弐百七拾六町五反六畝二十七歩 同三千百七拾九円九拾弐銭 藪壱町壱反壱畝二十九歩 同拾三円壱銭二厘 萱野四町五畝二十三歩 同四拾八円六拾九銭弐厘 芝地八畝歩 同三拾弐銭 秣場弐反歩 同弐拾八銭 | |
| 【飛地】 | |
| 田壱町四反五畝拾八歩 畑壱町壱反五畝二十壱歩 山林壱町八反三畝弐歩 総計反別四町四反四畝拾壱歩 本村西南々の方恩田川を隔て長津田村字麻生山(あそうやま)の内一ケ所にあり 田壱反六畝拾三歩 畑八反九畝二十歩 総計反別壱町六畝三歩 本村東南の方恩田川を隔て長津田村字北門堰(ほっかどぜき)の内一ケ所にあり 田三反二畝弐拾七歩 畑弐町壱畝壱歩 山林九歩 総計反別弐町三反四畝七歩 本村東南々の方恩田川を隔て長津田村字長津田耕地の内一ケ所に散在す | |
| 【貢租】 | |
| 金弐千六拾七円弐拾弐銭 | |
| 【戸数】 | |
| 本籍平民弐百弐戸、 社四 村一雑三 寺五 真言宗四 曹洞宗一 学校一、総計弐百拾弐戸 | |
| 【人数】 | |
| 本籍平民男六百七人 女五百七拾人 僧三人 総計千百八拾人 | |
| 【馬】 | |
| 牡馬三拾八頭 | |
| 【川】 | |
| 恩田川と称す 西南の方成瀬村より本村の西南堺字上和田に来り 南境を東に屈曲して長津田村との分界をなし 東南面の方字小山堰に来りて西八朔村へ入る 十日市場村の間長さ弐千七百弐拾間幅七間三尺より三間に至る 深さ平均三尺緩流にして清む 舟筏通ぜず | |
| 【溝渠】 | |
| 奈良川と称す 西の方奈良村より本村字井戸久保に来り東南に流し 西南の方 字山ケ谷(やまがやと)に来りて恩田川へ注ぐ 長さ四百五拾弐間 幅弐間より四間に至る 深さ平均四寸 一、は待堰堀(まちぜきぼり)と呼ぶ 西南西の方字樋の口にて前の奈良川を堰上げ村の南部を東南に流し 西南々の方字山ケ谷にて転じて東流し東南々の方字町田川に来りて恩田川へ注ぐ 長さ四百五拾弐間幅四尺より六尺に至る 深さ六寸田拾 五町弐反四畝九歩 一、は上和田堰堀という西南の方成瀬村にて恩田川に入り堰上げて本村堀の内に来り 東北に流して西南の方字内田に来りて前の奈良川へ合流 長さ五百八拾弐間 幅四尺より六尺に至る 深さ六寸 田拾七町三反九畝二十三歩 一、は堀切谷堀という 北の方字堀切谷の谷間の二所より発し村の北部を東流し 東北の方字広町より成合村へ入る 長さ三百四拾壱間 幅三尺 深さ弐寸 田壱町八反九畝拾九歩 一、は会下谷堀(えげやとぼり)という 東北の方字会下谷及び字広町の谷間三ケ所より発し 東北の方字成合にて一流となり北流し 東北北の方字広町に来りて成合村へ入る 長さ百六拾八間 幅二尺 深さ弐寸 田壱町八反八織拾三歩 一、は雨堤堀(あまづつみぼり)という 西北の方字雨堤の山間ニケ所より発し 東南に流し中央の梢東北を貫流して西南の方字小山堰に来りて恩田川へ入る 一、は三つ田谷堀(みつだやとぼり)という 長さ千六百九拾弐間、幅三尺 深さ四寸 田拾九町九反七畝七歩 西北々の方字三つ田谷の谷間より発し 東流して北の方一本橋に来りて前の雨堤堀に合す 長さ七拾壱間 幅壱尺五寸 深さ弐寸 田五反四畝二十歩 一、は清水口堀(しみずくちぼり)という 中央字清水口の谷間より発し 東流し東南東の方字榎田(えのきだ)に来りて前の雨堤堀に合す 長さ五百弐拾間 幅弐尺深さ三寸 田三町壱反二十八歩 一、は蝉谷堀(せみやとぼり)という 西北々の方字蝉谷の溜井より発し 相流し西南の方字六反田に来りて奈良川へ入る 長さ七百八間 幅弐尺より三尺に至る 深さ壱尺 田六町六反七畝拾壱歩 一、は白山谷堀(はくさんやとぼり)という 西北の方字白山谷溜井より発し 南流転じて南に流し 西の方字白山谷にて前の蝉谷堀に合流す 長さ五百六間 幅弐尺 深さ二寸 田六町七反七畝五歩 一、は鍛治谷堀(かじやとぼり)と呼ぶ 西の方字九郎次谷(くろうじやと)及び番匠谷(ばんしょうやと) 七郎右衛門谷(しちろうえもんやと) 大潰谷(おおつぶれやと) 西谷(にしやと)より発し東流し 西の方字鍛治谷に来りて合流して一流となり 西南西の方字内田前(うちだまえ)に来りて奈良川へ入る 長四百九拾弐間 幅四尺 深さ八寸 田拾町八畝拾八歩 | |
| 【溜井】 | |
| 西北の方字蝉谷にあり 東西三拾四間七分 南北拾壱間八分 面積四百九坪 深さ六尺 田上の用水に供す 一、は西の方字白山谷にあり 東西二十間 南北弐十間 面積四百坪 深さ六尺 田土の用に供す | |
| 【堰】 | |
| 本村より西南の方字山ケ谷 字奈良川にあり待堰という 土堰長さ八間弐尺 一、は東南の方字上和田にあり 上堰長さ七間 幅弐間修繕共に民費を以てす | |
| 【橋】 | |
| 大橋と称す 東西の方厚木往還字大橋恩田川の流れに架して往還を長津田村へ通ず 長さ七間六寸 幅六尺二寸五分 木製修繕民費に属す 一、は麻生山橋と呼ぶ 西南々の方村往還麻生山恩田川の中流に架して往来に通ず 長さ六間 幅六尺 木製修繕同上 一、は一本橋という 西南の方字一本橋の恩田川上流に架して往来を通ず 長さ七間 幅六尺 木製修繕同上 一、は内田前橋という 西南の方村往還字内田奈良川の中流に架し村往還に通ず 長さ三間 幅六尺 木製修繕同上 一、は井戸久保橋と呼ぶ 西の方村往還字井上久保の奈良川の上流に架して往来を通ず 長さ弐間三尺 幅六尺 木製修繕同上 一、は榎田橋という 東南東の方厚木往還字榎田の雨堤堀の下流に架して往還を通ず 長さ弐間三尺 幅六尺 木製修繕同上 一、は山ケ谷橋という 西南々の方村往還字山ケ谷の奈良川の下流に架して村往来を通ず 長さ三間 松七尺 石製修繕同上 | |
| 【道路】 | |
| 厚木街道に属す 東南々の方長津田村より本村字大橋に来り村の東部を東北は屈曲して通じ 東の方字サイカチ坂に来りて上谷本村へ連続す 長さ拾三町三拾五間 道幅弐間 | |
| 【掲示場】 | |
| 本村西南の方村往還の側字山ケ谷通元標の東北にあり 村の人口を距る事弐拾三町拾九間 | |
| 【社】 | |
| 神明社式外村社 社地東西拾壱間 南北九間 面積九拾九坪 本村西南々の方にあり祭神伊弉諾尊伊弉冉尊の二神を合祀勧請す 年月詳かならず祭日九月九日 杉山社 雑社 西南の方にあり 神明社 同 東南の方にあり 神鳥前川社(しとどまえかわしゃ) 同 同方にあり | |
| 【寺】 | |
| 徳恩寺 境内東西弐拾九間弐尺四寸 南北弐拾間 面積五百八拾ハ坪 紀伊国伊都郡高野山古義真言宗宝性院末流なり 西南西の方にあり 開基創建詳かならず 後建武二年三月僧等海これを中興す 医王寺 東西拾間壱尺弐寸南北拾弐間三尺面積百弐拾ハ坪本村の西南西の方にあり本村古義真言宗徳恩寺の末流なり 開基創建詳かならず 万福寺 貢租地にありて境内と称すべきものなし 本村古義真言宗徳恩寺末流なり 村の東南々の方にあり 唐安二年乙酉九月僧快秀開基創建す 寿光院 貢租地にありて境内と称するものなし 本村古義真言宗徳恩寺末流なり 村東南々にあり文明十年戊戌十月僧善養開基創建す 福昌寺 貢租地にありて境内と称するすのなし 本郡長津田村曹洞宗大林寺の末流なり 慶安年間僧大山開基創建す | |
| 【学校】 | |
| 四千七十六番公立小学恩田学校と称す 本村の南の方にあり 農高橋茂兵衛所有地に明治八年三月仮新築す 東西拾間南北三間面積三十坪生徒男六拾壱人 女弐拾五人 教員男弐人 | |
| 右者今般地誌御編集に付一村限詳載調査の上奉書上之処前証書載之通相違無御座候以上 第七大区七小区武蔵国都筑郡恩田村 明治十二年二月 戸長 神奈川県令野村靖殿 | |