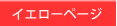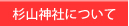新編武蔵風土記稿は文化・文政期(1804〜1829年)に編まれた武蔵国の地誌で全266巻。地誌取調書上を各村に提出させた上で、実地調査し、まとめた書物です。記されている内容は、地名、歴史、産業、神社、寺、土壌、風習など幅広く、当時の様子を知る貴重な資料でもあります。この新編武蔵国風土記稿にの恩田村の部分を下記に転記します。
| 恩田村 | |
| 恩田村は、郡の西相模国の界ひにあり、師岡庄に属す、江戸日本橋まで行程九里、村の広狭は東西へ凡一里、南北へも一里に餘れり、村の四境、東は八朔村に交り、南は鶴見川を隔てゝ十日市場・長津田の両村に及び、西は多磨郡成瀬村にて、北は又山を負て当郡鴨志田・成合・上谷本の三村につゞきけり、民家すべて二百五軒、此村も高低あり、水田多く陸田少し、いづれも谷間に開けり、土性は黒まさ土處により真土交れり、当村售領主は伝えざれど、北条分国の頃は小机の内恩田百廿七貫八百七十四文三郎殿と記せり、是によれば三郎影虎が知行なることしらる、後打入の後正保の頃は御医師岡本玄琳・清水亀庵・坂春也・齋藤摂津守・井戸信八郎が先祖忠兵衛等五給の外に徳恩寺の領あり、亀庵は何の頃にか上り地になり、伊奈半左衛門預り奉り、其後元禄十三年星合鍋五郎が先祖に賜り、齋藤摂津守釆地は、今の浅岡資格負御医師船橋宗迪が先祖に賜はれり、坂春也の釆地は其子孫壽三が時、故あって公に上しかば、柳澤佐渡守が先祖に賜はり、寺領ともに今すべて七給に及べり、検地は北条家分国の頃、天承十三年たゝせりと云、今其時の文書を村内百姓藤兵衛と云もの所蔵せり、その文によると検地にはあらず、段別ことに貢数をたて、その如く納べき由を記したれば、今の割付などいふものゝ類なるべし、されど古きものなればその全文を左にのす、 | |
| 酉年小机筋恩田之郷検地指出 一 参拾五町四段大九十歩 田数 此分銭 百七拾七貫四百五拾八文 但壱反別五百文宛 一 参拾三町半 此分銭 参拾三貫五十文 但壱反別百文宛秋成 弐拾壱貫五百四十七文 但壱反別六十五文宛夏成 合弐百参拾弐貫五十五文 田畑の辻 此内諸引物 壱弐貫百文 公事免但本途之辻十分一 五貫文 代官給 五貫文 名主免 参貫文 宮免 参貫文 井軒免 二貫文 定使給 以上卅貫百文 引方 残而 二百壱貫九百五十文 夏秋定納 以上 右当検地定納之辻無相違可致進納者也、仍如件、 天正十三年乙酉九月廿七日 奉行 小山筑前入道 中田加賀守代 柴崎但馬 恩田之郷 百姓中 |
|
| 御打入の後、元禄十一年柳澤・星合二人の給地を、伊奈半左衛門たゞし、寛文元年井戸の釆地をば、其地頭より検地せり、村内東の方に相州道あり、上谷本村より入長さ二十五町ほどをすぎて長津田村へ達す、道幅二間ばかり、秣場村の東北の間にあり、すべて三十丁ばかり、柳澤・星合等が知行の内なり、近村成合村のものこゝにて秣を刈とると云ふ、 | |
| 高札場六ケ所 村内所々にありしが、今は廃して二ケ所のこれり、 | |
| 小名 | |
| 下臺 | 町田川 早川 馬場 禅念寺村 五ケ所ともに南の方にあり、 | |
| 子の辺谷 | 村の西にあり、 | |
| 堀之内 | 西の方なり、から堀土人は城跡なりと云伝ふ、されば折ふし古陶器などのかけ損じたるもの出るといふ、 | |
| 牢場 | 西の方を云、 | |
| 井戸窪 | これも同じ辺なり | |
| 萬年寺谷 | 乾の方を云、 | |
| 仏山 | 村の中央をいふ、小高の所にして古碑あり、文字は漫滅して読べからず、 | |
| 秀林谷 | 東の方にあり、 | |
| 丸淵 | 村の西を云、川水をたゝへし小溝なり、干魃の時、雨乞いしてこの水を水田へそゝぐと云、 | |
| くみか淵 | 同じく西の辺にあり、 | |
| 八石山 | 村の北の方にある平山なり、 | |
| 子ノ神 | 同じ辺にある山を云、 | |
| 林二ケ所 | 村の北の方にあり、すべて一町三段あまり、柳澤佐渡守・船橋宗迪等が知行の内なり、 | |
| 鶴見川 | 村の南を流る、多摩郡成瀬村より入、村内を屈曲してながるゝこと一里許、東の方十日市場・八朔村との境に達す、川幅八間にして泥川なり、 | |
| 小川 | 村の北、奈良村より村内へ入、西南の間にて鶴見川へ合す、 | |
| 板橋 | 村の南の方相州道にて鶴見川に架す、長さ八間幅八尺の橋なり、 | |
| 橋 | 字麻生山と云所にあり、鶴見川に架す、作場道にわたす、長さ七間幅五間、自普請所なり、 | |
| 神鳥前川合社 | 見捨地、五段許、村の東にあり、石段数級を登りて丘上に社あり、二間半に二間西向なり、社前に鳥居をたつ、例祭は九月にて其日を定めず、神鳥前川と云は、祭神は詳ならざれど、神体は不動にて秘物なりと云、本社の左りの方に宮守の庵を置く、四間に二間ばかり、万福寺の持、 | |
| 末社天王社 | 本社に向ひて右の方にあり、 | |
| 神明社 | 見捨地、三段許、村の東の方にあり、南向なり、 | |
| 神明稲荷 | 村の西にあり、上屋三間に一間半、これも万福寺の持、 | |
| 末社天王社 | 本社に向ひて右の方にあり、 | |
| 杉山社 | 除地、三歩、村の西の方にあり、社は一間半四方、覆屋三間に四間半東向なり、例祭は九月十九日、村内徳恩寺の持、 | |
| 子野邊社 | 村の西より少く北の方によれり、上屋一間半に二間半、内に稲荷を相殿として小祠を置く、神体は石剱に似て長さ二尺ばかり、半より折てあり、円径三寸ばかりなり、是も徳恩寺持、以下同じ、 | |
| 稲荷四社 | 村内所々にありて何れもわづかづゝの除地あり、 | |
| 山王社 | 除地、一畝十歩、村の西堀の内通りにあり、 | |
| 山王社 | 除地、七畝二十八歩、 | |
| 天神社 | 除地、三畝八歩、 | |
| 御霊社 | 除地、二畝十五歩、 | |
| 第六天社 | 除地、二畝、字子ノ邊谷通りにあり、 | |
| 白山社 | 除地、二畝、村の北白山谷と云所にあり、 | |
| 徳恩寺 | 境内御朱印地の内、村の西柳澤佐渡守が釆地にあり、古義真言宗、高野山宝性院末、摩尼山延壽院と号す、開山は等海律師建武二年の開基にて、慶安六年三月三日寂せり、客殿十間に九間半東向なり、本尊虚空蔵坐像にて、長一尺ばかり、門東向なり、寺領七石は慶安二年八月二十四日賜はれり、 | |
| 寺宝 | 金剛薩埵の画像一幅 長二尺餘、幅一尺許、弘法大師の筆なり、何の頃にや当寺の僧高野山へ登りし時、譲受けしと云、至て古物なり、 | |
| 鐘楼 | 門を入て右の方にあり、一間半四方、安永八年の鐘銘あり、後證に足ざれば略す、 | |
| 弁天社 | 客殿に向て左の方にあり、四間四方、東向なり、木像にて一寸八分と云、秘して客にみることを免さず、湛慶の作なりと云、又正観音の像を安す、 | |
| 万福寺 | 除地、八段許、村の中央にあり、是も古義真言宗、徳恩寺末、興栄山信乗院と号す、開山快秀其年代を伝へず、二世を源長と云、慶安八年寂すとのみ伝て、月日を伝へず、客殿七間に六間南向なり、本尊薬師坐像にして長さ五寸許、 | |
| 護摩堂 | 客殿に向て右にあり、西に向ふ、堂は三間四方、不動の立像長一尺五寸なるを安す、 | |
| 鐘楼 | 客殿に入て右の方にあり、一丈三尺四方、宝暦八年に鋳し鐘なり、 | |
| 福昌寺 | 除地、三段許、村の西にあり、禅宗曹洞派、長津田村大林寺末、天龍山と号す、開山は国抽太山、慶安四年四月十五日寂す、客殿七間半に六間東向なり、本尊釈迦坐像にて長八寸許、 | |
| 観音堂 | 門を入て左りの方にあり、二間四方北向、十一面観音坐像長一尺ばかりなるを安す、 | |
| 稲荷社 | 客殿の後にあり、上屋二間に三間北向なり、此稲荷は地頭御医師師岡本玄冶より寄附せりと云、 | |
| 壽光院 | 年貢地、二丁許、村の東によりてあり、是も徳恩寺の末なり、安養山と号す、開山宣栄、延享三年十二月十日寂す、当寺第一世の僧を秀頴と云、弘治三年四月五日示寂すと云伝ふれども、其頃は僅の庵などにてもありしにや、今これを開山とせず、延享の頃を人の開山とする覚束なし、客殿七間に五間南に向ふ、本尊弥陀坐像長一尺二寸ばかり、境内に古碑一基あり、延文 年十月日と刻せり、是もいかなる人の碑と云ことを伝へず、はた此寺にはあづからざるものなるべし、 | |
| 医王寺 | 除地、二段許、村の北へよりてあり、同村徳恩寺の末、瑠璃山と号す、客殿三間四方、本尊薬師立像二尺あまり、行基の作と云り、開山は印興永正三年寂す、その月日は伝へず、 | |
| 地蔵院 | 境内年貢地、村の中央にあり、これも徳恩寺の末、太州山と号す、平屋作の家にて三間半に二間東向なり、本尊は地蔵坐像にして長一尺二寸ばかり、 | |
| 古墳 | 村の南相州道の内、石塔坂と云所にあり、登ること三丁許、半腹に五輪の塔あり、故にこの名ありと云、土人の伝ふる所は昔粕屋某と云もの当村に住せし頃、隣村長津田村の地頭某婚属なりしが、それらの人々をこゝに葬りし古墳なりとぞ、其五輪の臺石に鐫る文左にしるす、奉読誦法花妙典一千部、成就為判用道印十三忌、乃至利益不限而已、孝子相州恩田住 粕屋清印(敬白) 元亀四癸酉天三年五日、 | |
| 餓鬼塚 | 村の西の方にあり、僅の處に数七ケ所ありて、或は二間或は三間のさしわたしなり、土人云、古へ乱世の頃うえて死せるものを葬むるとぞ、今よりは定かには知べからず、 | |
| 念仏塚 | 村の西にあり、さしわたし二間ばかり、何も古墳と見ゆれど、伝をさだかにせず、 | |
| 古蹟寺蹟 | 万年寺と唱ふるは、村の南の方にあり、禅念寺と云は西北の方にありて、今は何も字にのみ残れり、むかし戦争の頃万年寺にある鐘を、陣中へうばひ行て、陣鐘に用ひ、後相州鎌倉郡瀬谷村妙光寺へ持行て今にあり、その鐘銘に、 武州恩田雷王鷲山、松栢万年禅寺者、行基菩薩草創、渉歳時也久異云云、于時正中二年乙丑年三月十七日万年禅寺住持比丘、道周、謹題、大檀那菩薩戒弟子廣鑑、また南謄部州大日本國中、相州瀬谷郷藤原朝臣山田伊賀入道経光、難執倍々利潤、質本主依置流之、爲大檀那奉寄進妙光寺矣、于時宝徳四年壬申卯月十六日 大工和泉守恒國とあり | |